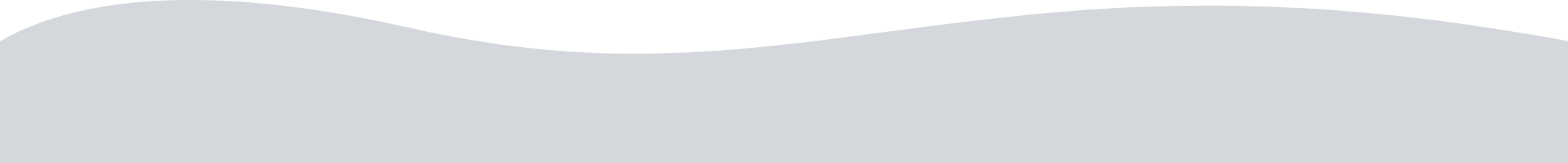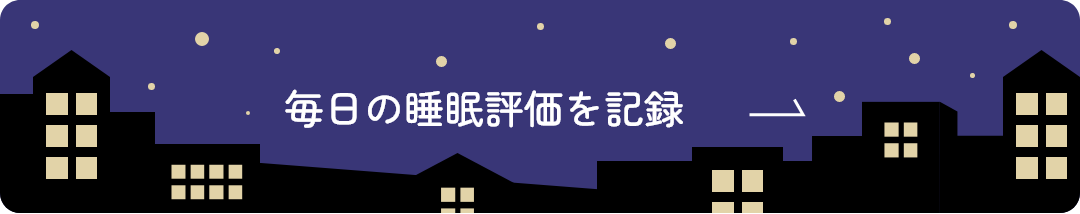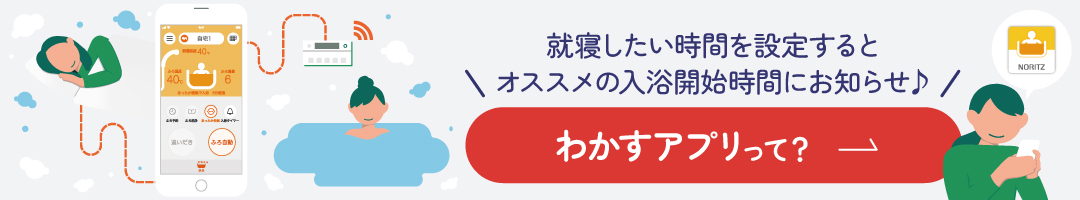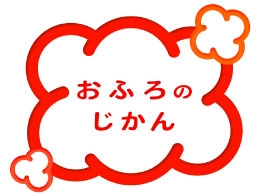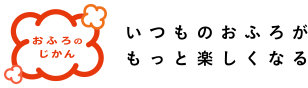睡眠不足が夏バテにつながる?身体を冷やさない睡眠環境の作り方

睡眠不足が続きやすい寝苦しい夏の夜。その疲れやだるさ、もしかすると「夏バテ」のはじまりかもしれません。例えば、冷房の温度設定を考えなかったり、風が直接当たる状態で寝てしまうと、知らず知らずのうちに身体が冷え、深い眠りが妨げられてしまうことも。このコラムでは、夏バテを防ぐカギとなる「質の良い睡眠」について、身体を冷やさず心地よく眠るための環境づくりを詳しくご紹介します。暑さに負けない毎日のために、まずは夜の過ごし方から見直してはいかがでしょうか。
睡眠不足が夏バテを招くメカニズムとは?

体調不良の連鎖を生む原因になるかもしれない「暑さで眠れない」「夜中に目が覚める」といった夏の夜の悩み。身体と心を回復させる大切な時間と認識されている睡眠ですが、熱帯夜が続くと寝つきが悪くなり、深い眠り(ノンレム睡眠)が不足しがちになると考えられています。すると、疲労回復やホルモンバランスの調整がうまくいかず、日中に倦怠感や集中力の低下、食欲不振など、いわゆる「夏バテ」の症状が現れやすくなるのです。さらに、睡眠中の発汗によって体内の水分とミネラルが失われやすくなるため、脱水や熱中症のリスクが高まることも。特に寝不足が数日続くと、自律神経が乱れやすくなり、体温調節機能に支障が出てしまうケースもあります。夏の体調不良は、睡眠の質と量に密接に関係しているのです。
夏でも「身体を冷やさない」眠りが大切
涼しい部屋で眠ると快適ですが、冷房の冷気が直接肌に当たると、表面温度が急激に下がり、自律神経にストレスがかかることがあります。特におなかや腰まわりなどを冷やすと、内臓の働きが低下し、免疫力が落ちてしまう可能性も。個人差があるため、あくまでも目安となりますが、冷房を使う際は、設定温度を「26〜28℃」の間に調整し、風が身体に直接当たらないようにするのがポイント。また、タイマー機能やサーキュレーターを併用して、空気を循環させる工夫も効果的です。そしてもう一つ大切なのが「寝具の見直し」。接触冷感素材のシーツや枕カバーを使いながらも、肌触りが良く、通気性に優れた天然素材を選ぶことで、冷えすぎを防ぎつつ快適な眠りをサポートできます。
心と身体をととのえる“温活睡眠”とは?

夜、眠る前におふろで身体を温めることも、夏バテ防止のカギになります。例えば、湯船に浸かる際は、ぬるめ(38〜40℃)のお湯に10〜15分ほど浸かることで、血行が促進され、リラックス状態をつくる副交感神経が優位に働きやすくなります。おふろ上がりの体温は一時的に上昇しますが、その後ゆっくりと下がっていく過程で自然な眠気が訪れ、入眠がスムーズに。寝つきが悪いと感じている人ほど、この機会におふろの時間を見直してみてください。さらに、ラベンダーやカモミールといったアロマを取り入れたり、部屋を間接照明で優しく照らしたりと、五感に心地よさを与える眠りの環境づくりも大切です。自分だけの「おやすみルーティン」を持つことで、夜の時間が癒しのひとときに変わりますので、ぜひ取り入れてみてくださいね。
ノーリツが発信する「おふろカレンダー」には、入浴行動による睡眠の影響への気づきをサポートしてくれる「睡眠の偏差値計測」をはじめとした睡眠機能があります。また、専用アプリ「わかすアプリ」で就寝予定時刻を設定すると、オススメの入浴開始時刻にプッシュ通知。さらに、ふろ設定温度と浴室温度から、オススメの退浴時間をお知らせすることで、おやすみ前の入浴習慣をサポートしてくれます。スッキリとした目覚めを実現するためにも、この機会にぜひコラム「ねむりとくらし」と併せてチェックしてくださいね。
※ご利用には、給湯機器専用アプリ「わかすアプリ」に対応する給湯機器とリモコンの両方が必要です。
「なんとなく疲れが取れない」「最近イライラしやすい」といったよくあるお悩み。暑い季節に感じる場合は、まず睡眠環境を見直すことがおすすめです。夏バテを予防するためにも、日中の過ごし方だけでなく、夜の休息時間の質を高めることで、夏を快適に乗り切る力につながるはずです。できることを少しずつ取り入れて、暑さに負けない身体と心を育ててください。
- 温まりかたや体感などには個人差があります。
- 体感や体調にあわせて、入浴時間・ふろ設定温度・ふろ湯量を調節して、無理なくお楽しみください。