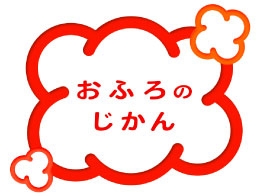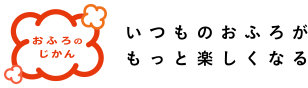Fashion
ロコモティブシンドロームとは?若者も高齢者も取り入れたい予防対策

近年、高齢者の健康知識として耳にする機会は増えたけど、まだまだ知られていない「ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome)」。骨や関節、筋肉といった運動器の衰えによって立つ・歩くといった基本動作が難しくなる状態を指し、「ロコモ」という略称でも呼ばれています。そして、高齢者だけでなく、若い世代でもその予備軍となっているのをご存知でしょうか。日々のちょっとした工夫が、将来の動きやすい身体を守る……ということで、今回はロコモティブシンドロームの原因と予防法、そして自宅で続けやすい温活エクササイズをご紹介します。
全世代に関係する「ロコモティブシンドローム」の原因

ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ)は、骨や関節、筋肉といった「運動器」に関わる機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態をいいます。進行すると転倒や骨折のリスクが高まり、将来の介護にもつながる可能性も。高齢者の問題と思われがちですが、実は運動不足や長時間のデスクワーク、偏った生活習慣により、20〜30代でも予備軍となるケースが増えているとされ、関心度が高まっています。
このロコモの背景には、加齢だけでなく筋力低下、柔軟性の欠如、骨や関節への負担の蓄積などが関わっているのも事実。現代では、便利さと引き換えに歩く機会が減り、階段よりエスカレーター、移動は車や電車などの公共交通機関に頼るなど、下半身をしっかり使う場面が減ってきています。このような生活が長く続くと、筋肉が衰え、バランス感覚や持久力が低下。気づかないうちにロコモが進行し、ちょっとした段差でつまずく、長時間歩くと疲れる、といったことにつながります。
ロコモティブシンドローム予防の基本は日常の動き

このロコモの予防には、特別な運動ではなく、「日常の小さな動き」を積み重ねることが大切。エレベーターをやめて階段を登り降りする、車や電車の移動を控え、少しでも歩く時間を増やす、お掃除ロボットだけに頼らず自分でも掃除をするといった「身体を動かす工夫」が予防につながります。また、下半身の筋肉を鍛えるスクワットや片足立ち、柔軟性を保つストレッチも有効。自宅や職場で取り入れ、習慣化することで、健康寿命を伸ばす身体作りを目指せます。
温活とエクササイズで楽しい気持ちで予防を

運動を習慣にするのが得意ではない人には、入浴と組み合わせた効率重視のエクササイズがおすすめ。湯船で身体を温めると、筋肉や関節が動かしやすくなり、血流もスムーズに。入浴後も身体が柔らかくなっているため、軽いストレッチや筋トレも無理なく続けられます。ノーリツで配信している「おふろワクワークアウト」では、入浴中の簡単な運動から入浴後のストレッチまで、温活と運動を組み合わせた方法を動画で公開中。バスタイムを活用すれば、日常生活に自然と運動が組み込まれ、ロコモ予防がより身近になります。
ロコモティブシンドロームは、早めの予防が肝心。若い世代であっても「まだ大丈夫」と思わず、今のうちから身体を動かす習慣を身につけることで、10年後、20年後の自分を守ることにつながります。日常のちょっとした動きと温活を組み合わせ、健康な身体をキープしてくださいね。
- おふろのあたたまりかたや体感などには個人差があります。
- 体感や体調にあわせて、入浴時間・ふろ設定温度・ふろ湯量を調節して、無理なくお楽しみください。