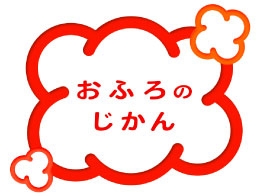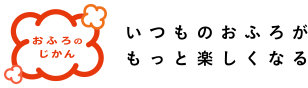Food
「1年で1番体調管理が難しい季節とは?」みんなのよくやる寒暖差対策をチェック!

立春を過ぎ、暦の上では春となる3月は、卒業や入学、入社など新しい生活が始まる時期であると同時に、1年の中でも体調管理が難しいとされている季節。特に3月から5月にかけては、朝晩と日中の寒暖差が大きく、身体にも負担がかかりやすいといわれています。そこで取り入れたいのが、日々の生活でも実践しやすい「温活」の習慣化。今回のコラムでは、寒暖差対策に役立つおすすめの温活方法をご紹介します。
「厚着・重ね着」だけでの寒暖差対策に頼らない!

寒暖差対策として、誰でも気軽に取り入れることができる方法といえば「厚着」「重ね着」。衣服で身体を温めることは必要ですが、これだけでは寒暖差のストレスを完全に防ぐのは難しいとされています。ある大手企業の調査によると、「厚着・重ね着以外の寒暖差対策を知らない」と回答する人が意外と多いという結果も出ているのだとか。対策を取らないままでは、寒暖差の影響をもろに受けてしまうことになります。
毎日の温活で寒暖差に負けない身体づくり

寒暖差に負けない身体づくりには、身体の内側から温める温活がおすすめ。ここでは、実践しやすい温活を3つ紹介しますので、この機会にチャレンジしてはいかがでしょうか。
疲れを癒しながら身体を温める「入浴」
寒暖差による自律神経の乱れを整える方法として、まず取り入れたいのが入浴。できればシャワーで終わらせず、ゆっくり湯船に浸かるのが、やはり一番早くて簡単な温活です。38〜41度のお湯に10分くらいを目安に浸かると、身体の芯から温まり、血流促進やリラックス効果も。1日の疲れをやわらげる効果も期待できますが、ダイエットや運動不足解消を意識したい方は、入浴エクササイズもおすすめ。ノーリツが発信している「おふろのじかん」では、入浴中にできる全身エクササイズ「おふろワクワークアウト」を動画で配信していますので、こちらもぜひチェックしてくださいね。
身体を温めながら腸も整える「食事」
食事も温活において重要なポイント。寒暖差に負けないためには、生姜やねぎ、かぼちゃ、人参など、身体を温める食材を取り入れることが大切です。温かいスープや鍋料理にすれば、身体を温めながら栄養もしっかり補給。さらに、食事温活は腸内環境を整える効果も期待できます。そもそも腸は、免疫細胞の約7割が腸に存在しているとされ、身体の免疫を司る大切な器官。オリゴ糖を含む食品(例えば、てんさい糖やヨーグルトなど)の摂取は腸内の善玉菌を増やす効果が期待できるのでおすすめです。
春の寒暖差に負けず、元気に過ごすためには、外側だけでなく内側から身体を温める習慣が重要。入浴や食事など、毎日の生活に温活を取り入れることで、体調を整え、不調を未然に防ぐことができます。寒暖差が厳しいこの時期こそ、自分の身体をしっかりケアするチャンス。ぜひ、温活を取り入れて、春を快適に乗り切りましょう。
- 記載した内容の効果は、個人差があり、記事の内容を保証するものではありません。
- ご自身の体調にあわせて、無理のない範囲でお楽しみください。
参考
春は、約9割が“寒暖差”を感じる、約7割が“体調管理が難しい”と回答 | 2024年 | キリンホールディングス