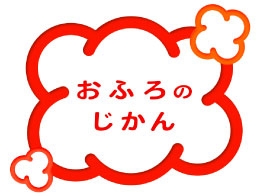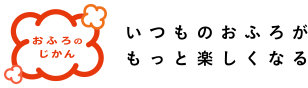Food
夏の冷房に注意!おなか周りを温める「子宮温活」って?

暑い日に、どうしても頼りたくなるといえばエアコン。家の中を快適な涼しさで満たしてくれるありがたい存在ですが、その“快適”が冷えにつながり、身体に影響を与えることがあります。そんなエアコンの冷え対策として、注目を集めているのが下半身を温める「子宮温活」。子宮温活で期待できる効果や具体的なやり方をこのコラムでご紹介しますので、この機会に覚えてみてくださいね。
「冷え」が身体に良くない理由

一般論として、女性の身体は男性より冷えやすいといわれています。そんな女性を悩ます「冷え」の原因のひとつが月経。そもそも月経期間は、血液量の減少により必要な栄養素を体内に届けることが難しくなる傾向があるため、エネルギーが不足し、身体の「冷え」につながりやすくなるといわれています。ではなぜ「冷え」が身体にとって良くないのか、理由をまとめてみました。
1.血行不良
身体が冷えるとは、血液の流れが悪くなること。言い換えれば大事な栄養素が身体のすみずみに届きにくくなり、老廃物を排出機能が低下しやすくなります。この状態が続くと身体のむくみや便秘にも影響が出るのです。
2.免疫力の低下
人間の身体は体温が1℃下がると、免疫力が約30%落ちるといわれています。免疫力が低下すると、細菌やウィルスなど外敵に対する抵抗力が弱まるため、病気や感染リスクが高まる可能性があります。
3.代謝の低下
体温が低下すると代謝量の低下にも影響が出ます。身体が冷えれば脂肪燃焼が難しくなり、ダイエットしにくい体質になることも。
幸せな身体づくりにつながる「子宮温活」

「温活」の原点は、“身体を温め、体温を適度な状態に上げるための活動”です。そして「子宮温活」とは“子宮に送られる血液を促進し、ホルモンバランスを整えること”を目的とした活動を指します。これを踏まえ、子宮温活が女性の身体にどのような影響を与えるのか、期待できる効果について紹介します。
病気のリスクが低下
血流を促進し、体温を上げることは免疫力の向上につながります。もちろんウィルスなど外敵に対する抵抗力が高まりますので、膀胱炎や婦人科系の病気の予防が期待できます。
代謝UPでダイエットにも◎
体温が上がると代謝が上がり、エネルギー消費量も多くなります。“太りにくく、やせやすい”という身体づくりにつながります。
妊娠に関わる機能を高める
子宮へ送られる血流を促すことは、妊娠に関わる子宮・卵巣の機能を高め、ホルモンバランスを整えることにつながります。
生理痛の緩和
女性の悩みで多い生理痛の原因にも冷えは関わります。子宮まわりを意識して温めることおにより、血流が促され生理痛の緩和につながりやすくなります。
今日からできる「子宮温活」

たくさんの「子宮温活」が出まわっていますが、誰でもすぐに始めやすい簡単な方法をご紹介します。
温活アイテムを使う
使うものはカイロや湯たんぽ。おへそ部分を覆うように当てるだけのシンプル温活は、おなか周りの血流が促進され、子宮に必要な酸素・栄養素が届きやすくなります。また、おなかだけでなく、上半身・下半身にも温熱が伝わり、身体全体が温まりやすくなります。(※カイロや湯たんぽを使う場合は、やけどにご注意ください。)カイロや湯たんぽは暑い!という方は、通気性・保温性にすぐれた腹巻などもおすすめです。
温活食材をいただく
根菜類や乾燥生姜は、身体を芯から温める作用が期待できるため、積極的に料理に取り入れたい食材。毎日の食事からも子宮温活につながります。
湯船に浸かる
体温を上げる最も手軽な方法なら湯船に浸かること。子宮周りを温めるのはもちろん、ストレッチなどを取り入れると健康にもプラスの影響を与えてくれます。おふろの時間で配信している「おふろワクワークアウト」では、入浴しながらできるストレッチやトレーニングが動画で公開されていますので、ぜひ参考にしてくださいね。
おふろワクワークアウト : https://ofuro-time.noritz.co.jp/wakuwork/index.html
エアコンで身体の冷えを感じたら、今日から「子宮温活」。毎日のライフスタイルに取り入れて、身体を温めてくださいね。
- 記載した内容の効果は、個人差があります。記事の内容を保証するものではありません。
- 無理のない範囲で行ってください。
参考
GUNZE: https://www.gunze.jp/kigocochi/article/1k202011-03/
島田総合病院: http://www.shimada-hsp.or.jp/_file/nukumori/no_04.pdf